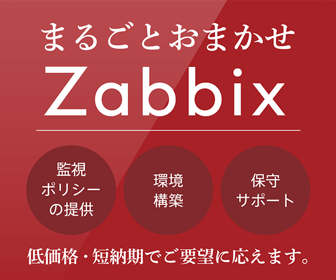リホストという選択肢:脱メインフレームの現場知見
こんにちは。システムマネジメントサービス1部の西川です。
私は日頃、お客様のメインフレームシステムの運用・保守に携わっています。
近年 IT業界では「脱メインフレーム」という言葉を耳にする機会が急増しています。背景には、メインフレームのハードウェアやソフトウェアの保守費用が年々高騰していることに加え、それらを支える技術者の高齢化や人材不足といった深刻な課題があります。
特に、長年メインフレームを活用してきた企業にとっては、今後も安定的にシステムを維持していくために、何らかの「脱却策」を講じる必要があります。しかし、長年蓄積してきた資産をどう扱うか、業務への影響を最小限に抑えるにはどうすればよいか――その判断は容易ではありません。
私が関わったあるプロジェクトでは、メインフレームからの移行を長期的視点で検討していましたが、予想以上に利用料が高騰することが判明し、早急な対応が求められる状況となりました。そこで私たちは、比較的短期間で移行可能とされる「リホスト」に着目し、調査と検討の支援を進めました。
結果的には現時点での「リホスト」実施は選択されず、メインフレーム延命に舵が切られましたが、支援を通して得られた学びを共有します。
脱メインフレームの手法とそれぞれのメリット・デメリット
いきなり「リホスト」と言いましたが、そもそも脱メインフレームの手法は「リホスト」だけではありません。
脱メインフレームにはいくつかの手法がありますので、代表的なものを紹介します。
| 移行方式 | 移行方式の説明 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| リホスト | 現行のソース・コードを極力そのまま生かして、基盤のみ別のプラットフォームに移行する方法 | ・短期間で移行可能 ・アプリケーションのロジックを変更しないため、業務影響が少ない ・システムライフサイクルの延長 | ・アプリケーション構造自体の課題はそのまま残る ・移行先インフラに合わせた体制の最適化が難しい |
| リライト | 既存のアプリケーションの機能やロジックを維持しつつ、コードを新しい言語やフレームワークで書き直す方法 | ・アプリケーションのロジックを変更しないため、業務影響が少ない ・メジャーなプログラミング言語の採用により、保守要員調達がしやすくなる | ・バグや仕様の再現ミスのリスク ・開発・テストに時間とコストがかかる |
| リビルド | 業務に影響を与えずに、アプリケーション・アーキテクチャを見直す | ・新技術を取り込める ・メジャーなプログラミング言語・技術の採用により、保守要員調達がしやすくなる | ・開発コスト、期間が大きい ・開発メンバーのスキルの切り替えが必要 |
| リプレース | 既存のメインフレームシステムを完全に廃止し、別のパッケージソリューションやSaaS、ERPなどの既製ソフトウェアに置き換える方法 | ・最新の業務機能やベストプラクティスを取り入れられる ・メジャーなプログラミング言語・技術の採用により、保守要員調達がしやすくなる | ・業務プロセスの大幅な変更が必要 ・既存のカスタム機能が再現できない可能性がある ・移行に伴うユーザー教育や業務調整の負荷が大きい |
リホストツールの比較
今回の検討では、2製品を比較しました。
- 製品A:COBOLやPL/I資産をほぼそのままLinuxなどのオープン環境で稼働させるリホスト製品
- 製品B:COBOL資産をWindowsやLinux上で再利用・実行可能にするランタイムおよび開発環境
それぞれの特徴を整理し、目的に応じた選定が重要であると感じました。


今回の対応を通して得た「学び」
今回の対応を通じて、最も重要だと感じたのは「脱メインフレームの目的を明確にすること」です。
目的によって、最適な移行手法は大きく異なります。
今回の検討を通じて、「どのような目的であればリホストが最適なのか」について、以下の2つの観点から整理しました。
リホスト後のシステムを継続利用するかどうか
リホストはメインフレーム上で稼働している既存の業務処理や運用処理のプログラムを、ほぼそのままの形でオープン系のプラットフォーム(LinuxやWindowsなど)に移行する手法です。コードの大幅な改修を伴わないため、短期間での移行が可能という利点があります。
ただし、既存のプログラム資産をそのままオープン環境に移行する手法なので、メインフレーム固有のレガシーなプログラム資産 (COBOL、JCL、バッチ処理など)はそのまま残るという点に注意が必要です。
つまり、インフラはオープン化されても、アプリケーションの中身は旧来のままであり、将来的な拡張性や柔軟性には限界があります。
目的が「既存資産の延命・インフラのオープン化」であれば、リホストは有効な手段と言えます。
COBOLを今後も使い続けるかどうか
レガシー資産であるCOBOLの開発・保守を続けるという方針が明確な場合、リホストは適しています。
しかし、将来的にJavaやC#、Pythonなどのモダンな言語に移行する方針がある場合、リホストは適していません。
また、COBOL技術者の高齢化や人材不足が進む中で、社内で技術者を育成・確保する意志があるかどうかも重要な判断材料です。
会社として「COBOLを今後も使い続けるのか」「それとも段階的に他言語へ移行するのか」という中長期的な技術戦略の明確化が、リホストの是非を判断する上で不可欠です。
今回の脱メインフレームの最終的な目的は「将来的なシステム刷新」でした。
リホストはあくまでインフラのコスト削減を目指した一時的な措置に過ぎず、結果的にリホストの実施は見送りになりました。
この経験から、脱メインフレームの手法を選定する際には、目的の明確化が最も重要であると強く感じました。
最後に
脱メインフレームは単なる技術移行ではなく、企業の将来像や技術戦略を見据えた意思決定です。
リホストはその中でも有力な選択肢の一つですが、目的や方針によっては「仮住まい」に過ぎないこともあります。
今回の経験を通じて、技術選定以上に「どのような未来を描き、それを目的として定義するか」が重要であると実感しました。
今後もお客様の課題に寄り添いながら、最適な選択肢を共に模索していきたいと思います!